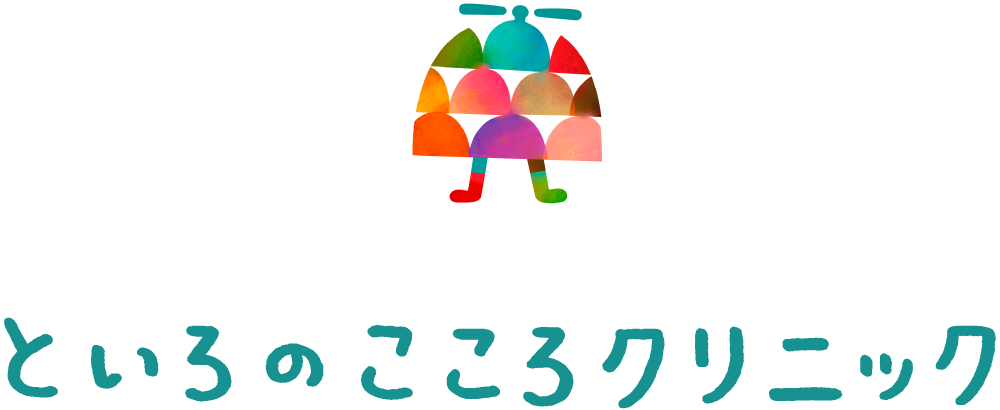注意欠如多動症とは
不注意をはじめ、多動や衝動性の特徴もみられる発達障害のことを注意欠如・多動症(ADHD)といいます。
そもそも不注意とは、集中力が続かない、気が散りやすいといったことがあります。さらにケアレスミスや忘れ物が多い、物事を計画的に遂行できない等も含まれます。多動は、落ち着きがない(手足をバタバタさせる)、席でじっと座ることができず、フラフラと歩き回る等の行動が現れるようになります。衝動性とは、順番を待つことが苦手で割り込みをしてしまう、人の話が終わらないうちにそれを遮ってまでしゃべり始める等がみられる状態をいいます。
なおADHDに関しては、成人になっても続くことは少なくないですが、多動・衝動性については落ち着くようになります。集中力が続かない、忘れ物をよくするといった不注意な行動はみられます。
ちなみに成人になってからADHDに気づくケースもよくあります。ただこの場合は、成人になってから症状が出始めたというわけではありません。単に本人も周囲も気づかず、社会に出るようになって、責任のある仕事を任せられるようになり、不注意等による様々な特徴や行動が露わになることで判明するといったパターンが多いです。
発症の原因は、はっきり特定されてはいません。ただ遺伝的要因も関係しているのではないかといわれていますが、それ以外の原因についても指摘されています。いずれにしても、親のしつけや養育環境が影響するということはありません。幼少期に発症しやすく、男女比では男子の割合が高く、その比率は3:1程度ともいわれています。
診断について
前述の症状が複数以上見受けられ、半年以上経過し、日常生活に支障をきたしているとなれば、注意欠如・多動症と診断されます。そのほかにも必要であれば、問診をはじめ、心理検査や知能検査を行なうこともあります。
治療について
まずは、気が散りやすくならないための環境を整える(集中しにくくなる物を隠す、一度に行う課題を短くして、こまめに休憩をとる 等)、感情のコントロールや他人の気持ちを理解する能力等のスキルを向上させていくソーシャルトレーニングを行います。また親などの養育者が、子どもの行動を適切にしていくために具体的な対応方法を学んでいくペアレントトレーニングや周囲がADHDに対する理解を深めていくことも欠かせません。
上記の対応だけでは不十分となれば、症状をコントロールしていくための薬物療法も併せて行います。主に、メチルフェニデート、リスデキサンフェタミンメシル、アトモキセチン、グアンファシン等が用いられます。