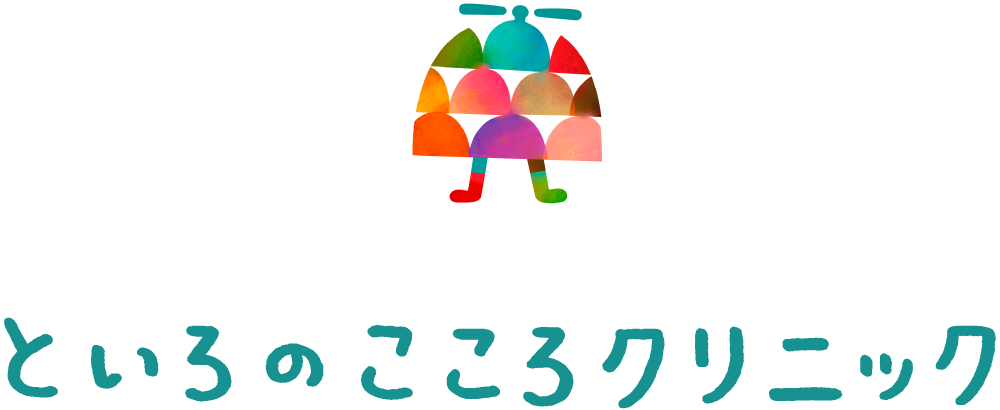発達性協調運動障害とは
個別に動くことができる手や足、目と手などの部位を一緒に動かして連動させることで、走る、ボールを取る等の動きをより正確に行えるようにするのが協調運動です。この運動には、脳や脊髄といった中枢神経も関わっています。
この協調運動が、神経疾患(脳性麻痺、筋ジストロフィ 等)を発症していないのにも関わらず、協調運動スキルの習得や使用が困難となっているのが発達性協調運動障害です。これも発達障害のひとつでもありますが、ADHDやASDなど別の発達障害と併存していることも少なくないです。
同障害では、例えば手と足を協調させた動きというのが難しくなります。人は意識をしなくても手足を連動させて歩くことができるわけですが、これが困難となれば、歩幅はバラバラ、身体のバランスもとりにくくなり、動きが不器用、動作が遅いといったことがみられます。比較的早期から症状は現れるようになるとされていますが、顕在化するのは幼児期の後期から小学校入学して学習が始まったあたりです。
この頃になると、ボタンを留める、紐を結ぶといった日常生活で必要な動作に時間がかかったり、物を落としたりします。また自転車に乗れない、はさみが使えない、運動が苦手といったことなども気になり、自らの動きのぎこちなさから気づくようになります。
発症の原因に関してですが、小脳に何らかの疾患があって発症することが多いです。例えば、小脳に先天異常がみられる、小脳腫瘍、小脳内での出血、小脳での血管障害などが挙げられます。また遺伝的な要因(脊髄小脳変性症 等)、薬物(抗けいれん薬 等)の影響などによって引き起こされることもあります。5~11歳の小児の5%程度に起きるとされ、男児が多いのも特徴で、男女比は2:1~7:1程度とされています。
治療について
完治させることは難しいですが、リハビリテーションやとレーニングを積んでいくことで、スムーズに身体を動かせるようにしていき、日常生活で不便さを感じている部分をできるだけ解消していきます。
リハビリテーション(作業療法、運動療法)としては、作業療法士と、手先の動作がスムーズになるように微細運動をしていきます。また理学療法士が傍らにつきながら、バランスボールやトランポリンを用いることで、姿勢を安定させたり、バランス感覚を向上させたりするなどします。また運動スキルを習得できるよう、ボール遊び、自転車の練習なども行います。
さらに環境調整として、ボタンが留めにくいのであれば大きめのボタンにします。また字が書きにくいということであれば太い芯の鉛筆を使う、靴紐を結ぶのが難しいのであれば、マジックテープの靴を履くなどしていきます。