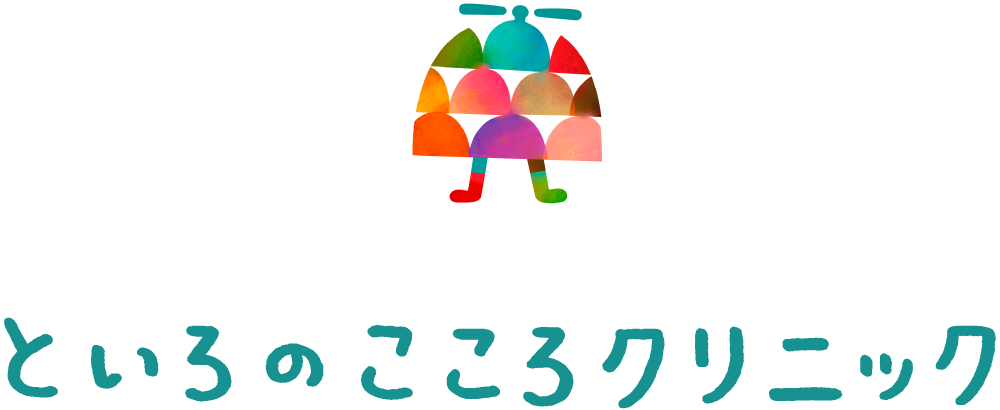知的障害とは
知的発達症とも呼ばれます。発達期(18歳くらいまで)に知的機能に障害が見受けられ、水準とされる領域よりも低く、さらに適応機能にも障害がみられます。これによって、日常生活や社会生活に支障が生じており、自立するには様々な支援が必要とされる状態のことをいいます。
知的障害と診断される基準は主に3つあるとされています。具体的には以下の通りです。
【知的機能の障害】
知能検査(新版K式発達検査、WISC 等)でIQが70未満
【適応機能の障害】
日常生活や社会生活を過ごすうえでの適応行動スキル(概念的スキル、社会的スキル、実用的スキル)が不足している
- 概念的とは文字の読み書き、数学的な思考、問題を解決する能力 等です。また社会的とは、人の気持ちを理解する、言語的・非言語的コミュニケーションの活用 等になります。最後の実用的とは、日常生活動作(着替え、排泄、入浴、身だしなみ 等)、健康管理、課題に取り組む等が含まれます。
【発達期に発症している】
18歳よりも前に発症がみられている
知的障害の重症度
一口に知的障害と言いましても、重症度によって、軽度、中等度、重度、最重度の4つに分類されます。知的機能(IQ)でも分けられますが、適応機能の障害度の方が重要視されます。
| IQの 範囲 |
適応障害の程度 | |
|---|---|---|
| 軽度 知的障害 |
51~70 | 日常生活動作は問題ない。言葉の発達はゆっくりで、抽象的な内容の理解は難しい。 |
| 中等度 知的障害 |
36~50 | 言語発達や運動能力に遅れがみられる。身の回りのことは、指示を受ければ部分的に行えるものの、完遂するのは困難である。 |
| 重度 知的障害 |
21~35 | 言語能力は制限され、運動機能の発達も充分でない。身の回りのことを自ら行うのは難しく、周囲のサポートが必要。 |
| 最重度 知的障害 |
~20 | 身の回りの世話は、他人の介助が必要。感覚・運動機能は、ほぼ発達していない。 |
原因について
発症の原因については多種多様です。ダウン症候群をはじめとする染色体異常や先天代謝異常症(脂質代謝異常、アミノ酸代謝異常、核酸代謝異常 等)があります。また、常位胎盤早期剥離等の低酸素性脳障害や頭蓋内出血等による周産期の異常、先天性甲状腺機能低下症や副甲状腺機能低下症といった内分泌障害のほか、出生後に発症した脳炎や髄膜炎などの後遺症や重度の頭部外傷といった出生後の出来事が引き金になることなどもあります。
治療について
知的障害には、完治させるための治療法というのはありません。この場合、療育と環境調整が重要となります。
療育では、早期から取り組むのは重要とされています。内容としては、望ましいとされる行動を学習していくことで問題行動を減らしていく行動療法をはじめ、言葉の発達が遅れている子どもには言語などを向上させる言語療法、日常生活動作(幼児期であれば、着替えや食事 等)などの発達を促進させるために練習等を繰り返す作業療法などを行っていきます。そのほかにも、対人関係やコミュニケーションスキルを学ぶソーシャルスキルトレーニング、保護者(養育者)が、子どもと適切に接することを学んでいくペアレントトレーニングも含まれます。
また環境調整とは、トレーニングや課題などをやりやすくする雰囲気づくりのことをいいます。集中力を欠くようなおもちゃ等をあらかじめ片付けておく、タイマー等を利用し、ひとつの作業を短くし、気持ちを切り替えやすくするなどしていくことで、できることを増やしていきます。