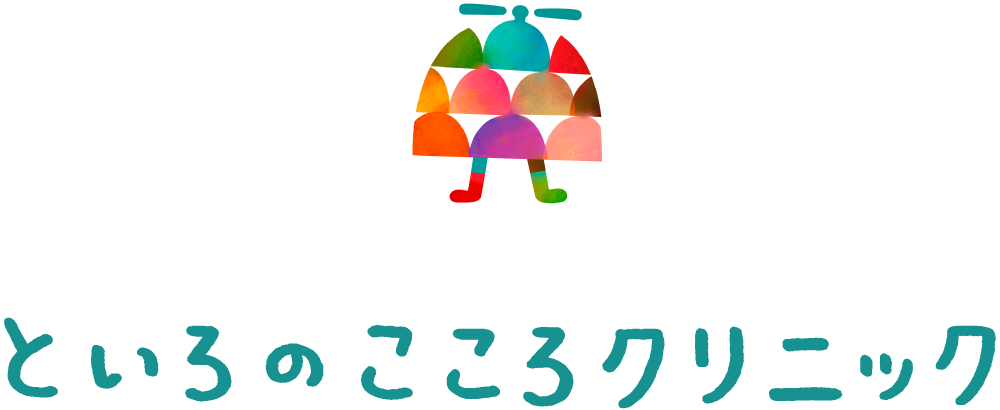場面かんもくとは
幼児期(2~5歳が多い、小中学校以降に発症することもある)にみられやすいとされ、家庭では普通に誰とでも話すものの、学校など場面が変わると何も話せなくなってしまう状態にあると場面かんもくの疑いがあります。発症率については、約500人に1人の割合とされています。
この場面かんもくというのは、本人の意思によって話さないというものではありません。極度の人見知りというものでもなく、話したくても話せないといった状況が続きます。なお、言語能力や理解能力に問題があるというわけでもないです。ちなみに場面によって話しができないというのは、1ヵ月以上は続くとされ、人によっては年単位と長期に及ぶこともあります。
これといった治療をしなければ、うつ病を併発してしまうこともあります。また成人でもみられることはあります。この場合、不安に苛まれる、すぐに緊張してしまうといった小児と同様の症状が現れるほか、会議や打ち合わせの場で発言できない等の症状が出るようになります。
場面かんもくは3つのタイプに分類
また場面かんもくは、症状の程度によって、軽症型、中間型、重症型に分類されます。軽症であれば、学校等で、話すことはできなくても、筆談ができ、スポーツ(球技 等)では、意思疎通は図れます。中間型でも家庭では問題なく話すことができます。ただ学校等では、周囲の人とコミュニケーションを拒否するほか、不安症状が現れるようになります。
重症型に関しては、家庭でも特定の人話すことができない、家族との場であっても言葉を発せられないということがあります。さらに学校など外の場面では、話すことができないだけでなく、身振りや手振りを含むコミュニケーションもしなくなります。また強い不安症状などから体が固まってしまい、思うように身体も動かせなくなる緘動症状が現れることも少なくないです。
発症の原因については、完全に解明されているわけではありません。ただ現時点では、社交不安障害が関係している、話すことにストレスを感じている、不安や緊張を感じやすい性質である等が挙げられています。このほか、発達障害の二次障害としてかんもくの症状が出ているということもあります。
なお場面かんもくを確定させる明確な診断方法はありません。この場合、患者さんに現れている症状であったり、ご家族や周囲の人々の話を聞いたりするなどして、診断をつけていきます。
治療について
治療に関しては、主に精神療法と薬物療法があります。
前者では、話しやすくなる環境を作っていくことが大切です。内容としては、認知行動療法によって、不安を感じるようになる気持ちの持ち方、これまでの自らの行動等を修正していきます。また不安を感じてしまう場面に段階的に馴れていくことで、話すことに対する抵抗感を減らしていく、系統的脱感作法というのもあります。
薬物療法に関しては、医師が必要と判断した際に抗不安薬やSSRI(選択的セロトニン再取り込み阻害薬)などが用いられることがあります。