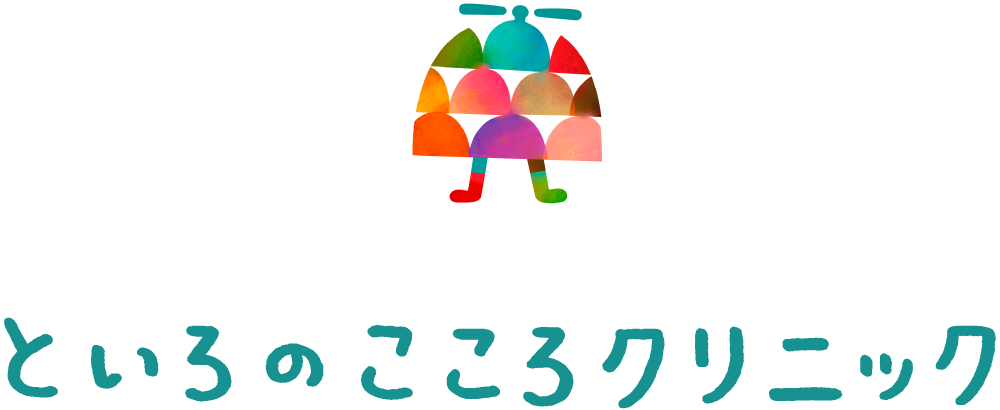チック症とは
本人の意思とは関係なく、突発的で不規則な運動や発声がみられ、これらが一定期間もの間、持続していると、チック症と診断されます。多くは男児にみられ、4~6歳くらいまでに発症し、10~12歳の頃は症状が強く出るとされるピークです。その後、成人になる頃には症状は治まっていきます。
発症の原因は特定されていませんが、脳内で分泌される神経伝達物質(ドパミン 等)が関係しているのではないかともいわれています。また、不安や緊張が強いられるようになると症状が悪化するということもあります。
運動チックと音声チック
一口にチック症と言いましても、大きくは運動チックと音声チックに分けられます。
運動チックは、主に体の動き(動作)ということになります。よくみられるのは、まばたき(目をパチパチ)、肩をすくめる、顔をしかめる、首を振るといったものが見受けられます。これらは単純運動チックと呼ばれ、複数の単純運動チックが組み合わさって現れている状態が複雑運動チックです。この場合、自らを叩く、飛び跳ねる、物に触れるなどの行動がみられるようになります。
音声チックでは、とくに意味がないとされる発声や呼吸音が聞かれるようになります。鼻を鳴らす、咳払いをする等の音を発するようになります(単純音声チック)。また、その場では似つかわしくない単語やフレーズを繰り返すこともあれば、汚い言葉を発することもあります(汚言症)。これらは複雑音声チックに含まれます。
なお上記のチック症の症状が出現してから1年未満にあると一過性チック症、1年以上経過していると慢性チック症と診断されます。また様々な運動チックと音声チックの症状が1年以上続いているとなれば、トゥレット症と診断されます。これはチック症の最重症型ともいわれています。
治療について
軽度であれば特別な治療を行うことはありません。ただチックの症状が出ていることを指摘したから治まるということはないので、周囲の理解というのも大切です。また必要と医師が判断すれば、精神療法(認知行動療法)を行います。内容としては、チックを抑制するための代替行動を学んで実践していく習慣逆転療法などがあります。
チックの症状が重症、あるいはトゥレット症の患者さんである場合は、薬物療法も行われます。この場合、ドパミン拮抗薬(リスペリドン 等)、不安障害が併発しているのであれば、抗うつ薬や抗不安薬が用いられることもあります。